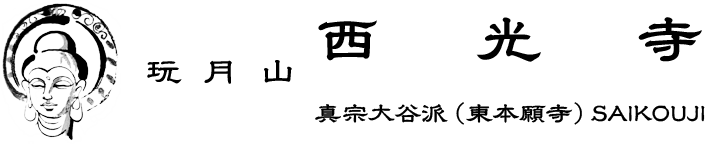ジャータカ物語
仏典童話
お釈迦様の前世物語。本生譚(ほんじょうたん)と漢訳されるお釈迦さま前世において菩薩であった時代に衆生を救った善行を集めた物語です。パーリ語聖典には五七四のジャータカ物語があり、散文と韻文とからなり紀元前三世紀ごろ成立といわれている。その後仏教の伝播に伴って世界各地に伝えられ、『イソップ』や『アラビアン・ナイト』などのペルシャ・アラビア寓話文学に深い影響を与え、日本でも『今昔物語』『宇治拾遺物語』などの中に散見される。
この物語について大谷大学の一楽先生はその著作に「釈尊が生まれる前のことは、「ジャータカ」という物語に膨大なものが残されています。前生譚(ぜんしょうたん)とも言われますが、いろんな物語があります。釈尊はあるときには鹿の王様だったり、兎であったりなど、いろいろ出てきます。しかし、それが実際にはどうであったかという詮索よりも、何を伝えようとしているかが大事だと思います。釈尊は人間界だけではなく、ありとあらゆる世界の苦しみ、問題を見尽くしたお方であると表しているのですね。ありとあらゆる世界の苦しみを見通した上で、敢えて人間の世界においてその問題をどう超えていくのかということを課題として担われたのが釈尊であると表現しているのです。
(『大無量寿経講義-尊者阿難、座より起ち-』文栄堂から)
これは、30年ほど前、住職が本山で「ラジオ放送『東本願寺の時間』」を担当していたときに放送されたものです。

仏典童話
タイトル
ムニカ豚の報い
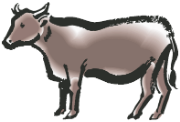
その名をマハーローヒタといい、その牛にはまたチュルラローヒタという弟があった。この二匹の牛の仕事といえば朝から晩まで車を引く重労働だったのです。ところでこの長者には年頃の娘があり、結婚も決まり、その準備に明け暮れていた。

そしてつぎのような詩を唱えた。
豪華な食事をうらやむな。死のご馳走なのだから。
欲を離れてモミを食べ、いのちの味をかみ締めようやがて婚礼の日が来て豚のムニカは殺されお客をもてなす料理になってしまった。

祇園精舎 釈迦香室跡
タイトルへ戻る
象と猿と雉のはなし
昔々、ヒマラヤ山の中腹に大きなニグローダという木があった。そしてその木の周りにキジとサルとゾウの三匹が勝手気ままな生活を送っていた。ある日のこと、こんなバラバラな生活はよいことではない、三人の仲間内で誰が一番年上かを調べて、年上の者を敬い、きちんとした暮らしをしようということになった。
そこで三匹はニグローダの木の下に集まり、まずキジとサルがゾウに向かってたずねた。「ゾウ君。君はこのニグローダの大木をいつごろから知っているのだ?」ゾウはゆっくりと長い鼻を振り上げながら「うーん、ボクの子どものころはこのニグローダの木はひざにまで届かない若木だった。だからボクはその上をまたいで通ったものさ。それからおとなになってからもこの木の先はボクのへその辺りまでしかなかったなあ、いずれにしてもそんな小さいときから知っているよ。で、サルくん、君はどう」

「そうだな…。昔ここからずーっと離れた場所にやはり一本のニグローダの木があって、私はいつもその実を食べていた。その私がここへ来て糞をしたもので、その中に混じっていた種が芽を出してこんな大木に育ったというわけ。だからこの木の生える前から知ってるということになるね」
「そうか、だったらキジさん、あなたが一番年上ということになるね。これからボクたちはあなたを先輩として敬い、いろいろ教えてもらうことにしよう。よろしくね」
それからというもの、キジは規律正しい生活を二人に授け、自分もまたその規律を守って暮らした。そして三匹の自然で安らぎのある生活が続いていった。

舎衛城跡
“真理を求めるものはまず先輩を敬うべし
それが未来を開く第一歩となる”
さらに続けてさっきの話のゾウは目連、サルは舎利弗、キジこそは前(さき)の世の私であった、と言葉を結ばれた。
鳥さしとウズラ
昔、ブラフマダッタ王がバーラーナシーの都で国を治めていたころのことである。一人の菩薩(ぼさつ)が鶉に生まれ変わって多くの仲間とともに森の中に住み着いていた。その近くに一人の鳥射しがいて鶉を捕らえて暮らしをたてていた。囮(おとり)の口笛が抜群なので鶉はどんどんおびき寄せられていく。ある日菩薩は仲間たちに向かって訊ねた。
「このままいけば我々は全滅してしまう。みんなはそれでもいいのか?」重苦しい沈黙が流れる中で一羽が力なく「だけど、どうしようというのです。あの鳥射しの口笛の誘惑、それにあっという間に襲い掛かってくる網の目から逃れる方法があるとでもいうのですか?」
「ある。」菩薩はこたえた。
「あるとも、力を合わせることだ。いいか、網が投げられたらみんな網の目に頭を入れて、力いっぱい羽ばたくのだ。みんなが力を合わせればきっと飛び立つことができる。そして茨の藪に網を捨てよう。そうすれば鳥射しが網を探すのに丸一日はかかるだろう。」

次の日も、また次の日も鳥射しは鶉の群れに振り回された。ぷりぷりして家に帰ると、 「お前さん、今日もまた手ぶらじゃないか。他に持っていくところでもできたんじゃないの!」妻までが嫌味たっぷりに言う。
「馬鹿いうな!嘘だと思うなら森までついてくればいいだろう。フン、こんなことが長続きするもんか。」
幾日かが過ぎた。餌場に舞い降りた鶉の群れにとうとう喧嘩騒ぎが起こった。
「いばるな!自分ひとりで網を持ち上げているわけじゃないぞ」
「なにをー、もういっぺん言ってみろ!」
この様子を見て菩薩はこれでは一族のすべてが滅びると考え、周りの弟子たちを連れて新しい森へ飛び去っていった。
一方森に現れた鳥射しはまだ喧嘩に夢中になっている群れをめがけて網を投げ、一羽残らず捕らえて籠につめた。妻の喜ぶ顔が浮かんで鳥射しは自分もニヤリとほくそ笑んだ。
お釈迦様はこう語り終えられ、“争いはすべて滅亡の元である。一族の間で争ってはいけない。そのときの智恵ある鶉こそ前の世の私であった”と、言葉を結ばれた。
タイトルへ戻る
山犬のたくらみ
昔、ブラフマダッタ王がバーラーナシーの都で国を治めていたころのことである。一人の菩薩が大ねずみに生まれ変わって、数百匹の手下を連れ、林の中に住んでいた。

そこでいつもネズミたちが通る丘の上にまっすぐ太陽に向かい、風をいっぱいに吸い込んで片足で立った。
「へっへー、誰が見ても立派な修行者に見えるだろう。」
山犬はひとり得意げである。一方ねずみになった菩薩はいつものように一族を連れてえさを探しに出かけ、この丘を通りかかった。
「ここで何をなさっているのですか?」ねずみの菩薩は進み出て尋ねた。
「ウン、ウーン。何に見えるか?」
「修行中のお方だと思います。名前をお聞かせください」
「あ、ウーン、宇宙の根源という名じゃ。」
「一本足で立つ修行なのですか?」「
いやーそうではない、四本足で立つと大地がわしの重さを支えきれないのじゃ」「口をあけておられるのは?」
「か、か風を喰っておる。遠い海の香りを運ぶ風。谷から吹き上げる冷たい風、みんな味がちがってなかなかうまいもんじゃよ」
「太陽に向かっておられるのは?」
「礼拝しておる。太陽もまたわしだけを照らしておる。」
「ほぉー、偉い方なのですね。これから毎日私どもはあなたのお姿を拝みにまいります。」 山犬は内心シメタと思った。
それからネズミたちは朝晩この丘にやってきて、山犬に一礼してから帰る習慣がついた。ところがネズミたちが列を作って帰るときになると、列の一番後ろの一匹をパクリと一飲みにしてしまうのである。ねずみの数はだんだん減っていった。
そこで次の日菩薩は自分が列の最後になり、用心しながら帰ろうとしたそのとき突然背中に殺気を感じた。ねずみの菩薩は振り向きざまにさっと飛び上がり、山犬ののど笛を噛み切った。そして息絶えたのを見届けて次の詩をとなえた。

お釈迦様はこう語り終えられ、そのときのねずみの菩薩こそ前の世の私であった、と言葉を結ばれた。
タイトルへ戻る
ビサーラの恩返し
昔、ガンダーラーの国タッカシーラの都で、ケンダラ王が国を治めていた頃のことである。
一人の菩薩が仔牛になってこの世に生まれた。まもなく若く貧しい農夫がこの仔牛を手にいれ、ビサーラ「喜び」と名づけた。ビサーラは野山を自由に駆け回り、力強くたくましい牛に成長した。そして若者だった農夫は貧しいまま年老いていった。
ある日、ビサーラは主人に恩返しがしたくてこういった。
「私をこんな立派に育ててくださったので、なにかお礼がしたいのですが、今一番ほしいものはなんですか?」農夫はしばらく考えていたが、
「そうだなあ。一生懸命働いてやっと貯めたお金が1000キン、できたらあと1000キンはほしいのだが」

「よろしい、村の長者の家に行き力比べの賭けをなさい。荷物を満載した百台の車を一列につないで私が引きます、これが動けば1000キン。きっと勝たせて差し上げます。」
農夫はさっそくビサーラを連れて長者の家に行き、うまく長者を煽って賭けを挑ませた。たちまち下男たちが呼ばれて材木や石を満載した百台の車が門前にずらり。
「さぁー、はじめよう。動かなんだら1000キン間違いなく申し受けるぞ!」農夫は荷台の先につないだビサーラにピシリと鞭を一当て
「そら引け、畜生め!」と叫んだ。ビサーラは動かなかった。
「コンチクショウ、どうした、鞭がいくつも飛んだ。ビサーラはそれでも動かず農夫はかけに負けて全財産1000キンを取られてしまった。
とぼとぼと家路に着きながら
「ビサーラ。どうして私を騙したりするのだ?」
「あなたは私を畜生と呼ばれた。そんな蔑んだ呼び方で私が動く気になれますか?」農夫はうなだれた。
一度長者のところへおいでなさい。そして今度は200台の車を引かせ、2000キンの賭けをなさい。
2000キンを賭けた200台の荷車の先にビサーラはいた。農夫はビサーラの首をやさしく撫でて
「ご苦労だな、力を出しておくれ。頼んだよ」ビサーラは息を止め、満身の力を込め、舵棒を引いた。ギシっという音と共に200台の車は動き始めた。農夫は賭けに勝って2000キンを手にした。
お釈迦様はこう語り終えてから、“言葉は愛を伝えるためにある”と一言付け加え、このビサーラこそ前の世の私であったと、言葉を結ばれた。
タイトルへ戻る
吊り橋になった母猿
昔、バーラーナシーの都でブラフマダッタ王が国を治めていた頃のことである。

「はぁーい。うれしいな。今日はおなかいっぱい食べられるぞ。早く行こうよ、おかあさん」はしゃぎまわって木の枝はもう折れそうである。
「だけど今日は一つ大事なことを言っておきますよ、おまえたちはどんなことがあってももぎ取ったマンゴーの実を川の中に落としてはだめよ。もし一つでも落としたら実は丸一日かかって川を流れ、川下に住む人間に拾われます。人間はこんなおいしい果物を知らないから、きっと大勢でこの実を探しに来るに決まってる。そしたら私もおまえたちもここから追っ払われるのよ。いいね!」
マンゴーの木はガンジスの流れに覆いかぶさるように枝を伸ばし、先に行くほど良く熟れた実がなっていた。歓声をあげた小猿たちは枝から枝へ飛び移って甘いマンゴーの実をおなかいっぱい食べ、陽が西にかたむくまで楽しいときを過ごした。

母猿が皆にそう言った時一番小さい小猿の手が滑ってマンゴーの実がひとつ川の中へ落ちていった。
「おかあさんはあんなこと言ったけど一つくらいいいや、どこかへ沈んでしまうだろう」
小猿はそう考え黙っていた。川の流れは早くなったり遅くなったりしてその実を都へ運んでいった。
「なんだろ、これは」
都に近い岸で魚を獲っていた漁師が拾い上げ、
「いい香りがする。見たこともない果物だ、こんな珍しいものは王様に差し上げたらどうだろう。きっと何か褒美がもらえるぞ」
そういってお城に持っていった。
「ホォーッ」マンゴーの実を食べた王様はいたくご満悦である。そしてそのおいしさが忘れられず、とうとうこれを探しに出かけることになった。
「すぐ兵を用意せよ!五隻の船に兵隊を乗せガンジスを何処までもさかのぼるのじゃ。この実がなっている木が必ずある、急げ!」
すぐ軍隊が出動し、王様の船を先頭に上流にむかって漕ぎ出した。船は営々と丸一日漕ぎ続けられマンゴーの木に近づいた。
「あっ、あれだ!あの木だっ。鈴なりだあ。みごとな実をつけているではないか。あん、木の上で動いているのは何じゃ。ん、な、なに猿だと!けしからん!弓だ、弓をもてーっ。」
王様とその兵隊たちは船の上から猿の群れ目がけて次々と矢を射かけた。
「さあ、みんな逃げるんだよ、あわてないで。この枝を伝って向うのニグローダの太い枝に飛び移ってお行き、わかったね」
大きい子どもたちは次々と力いっぱい飛び移って、矢の届かないニグローダの茂みに隠れた。
「おかあさん、こわいよー。ボクたち飛べないよ」
マンゴーの木には100匹の赤ちゃん猿が残った。
「じゃ、お母さんがこの藤蔓を体に結び付けて先につかまるからね、みんなはそれを伝って向こう側へお逃げ、順番に落ち着いて渡るのよ。さあ、早く!」小さい猿たちは震えながら藤蔓と母猿の背中を伝って渡っていく。「お母さん、痛くない?」「お母さん、手がしびれてるでしょう」
「お母さん、離さないで」母猿は数えた「95、96、97」あと三匹。手が千切れそうに痛み、藤蔓を巻いた胴は締め付けられて息が止まりそうになる。98、99そして最後の小猿が頭を踏んで渡りおわったとき、母猿の手は枝から離れ、ガンジス川の深みに飲まれるように落ちていった。
「おかあさーん!」

“我が身を吊り橋にして子どもを助けた母猿哀れ、あの猿を救え、マンゴーの実は二度と採るまい”
お釈迦様はこう語り終えて、そのときの母猿こそ前の世の私であった、と言葉を結ばれた。
タイトルへ戻る
象を倒した鶉
昔、バーラーナシーの都でブラフマダッタ王が国を治めていた頃のことである。
ひとりの菩薩が象の群れに生まれて、その王者となった。体はどの象よりも大きいが心は優しく、八万頭の仲間を引き連れヒマラヤの高原を駆け巡っていた。
そこに一羽の鶉がいて、象の群れが通る道端に卵を産んでしまった。卵は孵ってかわいい雛が生まれたがまだ飛べない。そこへ王者を先頭に象の群れがやってきた。親鳥は驚いて飛び立った。
「象の王様、王様。そのように急がないでくださいまし。この先に私どもの巣がございます、そこにはまだ飛ぶことのできない私の雛がおります。どうぞ気をつけてやってください。」
「オウそうか。それは良く知らせてくれた。ワシの一族が通り過ぎるまで巣の前に立って守ってあげよう」
八万頭の像は列を作って鶉の巣の前を通った。
「ところで鶉さん、この後からもう一頭『はぐれ野郎』と呼んでいる象がくる。そのものにも良く頼んで子どもを守ってやりなさい。」
鶉は両の羽で合掌した。
やがてはぐれ野郎が現れた。
「象さん、はぐれの象さん。この先に私の子どもがいます、どうか踏みつけないようにお願いします。」
「なーにぃ。子どもに気をつけろだと!へっ、弱いものはなにをされても黙っているもんだ。それが自然の習いってもんさ」
はぐれ野郎はそううそぶいて鶉の雛を踏み潰して去った。鶉は泣いた。体が融けていくほど泣いた。そこへ友達の烏とハエとヒキガエルがやってきた。仲間の慰めと励ましの言葉に鶉は涙を払って
「アイツを生かしておいてはこの先次々と私たち弱いものを踏み潰していくでしょう。今ここで力を合わせて戦いを挑まないこと?どうカラスさん。あなたはあいつの目をそのくちばしで潰してよ」
「いいとも、ちょっとおそろしいけどみんなの為だ。」
「ハエさんはあいつのつぶれた目に卵を産みつけてちょうだい、早くウジがわくようにね」
「それでボクは?」

「わかった、奴が崖っぷちに来たら今度は谷底で鳴くんだね」
すべては計画通り運んだ。目の痛みに耐えかねたはぐれ象は水を求めてカエルの声を頼りに崖っぷちに誘われ、谷底に転がり落ちて息絶えた。
お釈迦様はそう語り終えられ、そのときのはぐれ象はダイヴァダッタであり、象の王者こそ前の世の私であった、と言葉を結ばれた。
タイトルへ戻る
池の柳
昔、ひとりの菩薩が森の中の蓮池の畔に一本の柳の木となって生まれた。
この蓮池は夏になると決まって水が枯れ、そこに住む魚たちが何百匹も死ぬのであった。それを知った一羽の青鷺が、どうせ夏になって水が干上がり、魚たちが死んでしまうのなら今のうちに俺が食ってやろうと考えた。

「青鷺さん、憂鬱そうなお顔ですね、どうかしましたか?」
水の中から一匹の魚が聞いた。青鷺はますます心配そうな表情で大げさに嘆いて見せた。
「ハーッ、君たちはなんにも知らないんだね、私が心配しているのは実は君たちの事なんだ。」
「僕たちのこと?」
「そうとも!魚だけじゃない蟹やタニシ小エビや蛙君ら水の中に住んでいるみんなのことだよ。いいかい、この池は夏になると水が無くなって、底はひび割れ、君たちは一塊になってのた打ち回るようになる。それを思うと夜も眠れないほど苦しくてネ」
「なーんだそんなこと!水が無くなったら僕たちは生きていられない。それは僕たちみんなが背負った運命と言うものさ」魚は明るい声で答えた。
「水が枯れて死んでしまうんだよ、知ってるかい?」
「それは僕たちが背負った運命というものです」
魚は明るい声で答えた。

魚たちは額を寄せて相談し、代表として一匹のヤモメの魚を選んだ。青鷺はそのヤモメの魚を咥え、森を二つ飛び越し山の向うへ飛んだ。湖は透明な水をたたえ、浅瀬は五色の蓮の華で覆われ、取り囲む緑の森がふかみに美しい影を映していた。
湖から帰ってきたヤモメの魚はその素晴しさを仲間に語り、その上
「湖の景色もだがそれより俺たちの好きな藻や水草が食べつくせないくらい繁っているんだぜ」
と付け加えたからたまらない。魚たちはわれもわれもと移住を申し出た。

「ウゥーン、ヒッ。たわいのない奴らだ。魚の肉ばかり食ったので何か一口硬いものがほしい。あそうだ、蟹の甲羅など歯ごたえがあっていいかもしれん」
青鷺は蓮池に舞い戻り、水の中の蟹を呼び出した。

「いままで魚を獲っては食べていたあなたが急に魚の身の上を心配するなんて、ボクには納得できないな。」
「それそれ、君の考え深いのはいいよぉ。でも過ぎたるはなんとかっていうじゃないか、私はもう二度とここへは来ない、最後のチャンスだと思ってわざわざ君に声をかけたんだ、あとで後悔しても私はもういないよ」
「うーん、そうだね。そんなにまで言ってくれるなら。じゃあ、僕も連れて行ってもらおうか。だけど行くときはボクのはさみで君の首に捕まらせてくれないか?」
「いいとも、そのほうが私もくちばしが疲れなくてけっこうだね」
青鷺とカニは宙に飛んだ。第一の森が近づいた。青鷺はカニを叩きつけるのにふさわしい枝を捜し探し飛んでいく。そのとき夥しい魚の骨と頭が蟹の目に映った。蟹は青鷺の首を挟んだはさみに力をいれた。
「だましたね!やっぱり。」
口調は静かだったが怒りがこもっていた。
「親切ごかしをしてみんなをだましたね」
はさみにいっそう力が入った。青鷺は息も絶え絶えになり、一言もしゃべれない。地面に降りたったときには息は止まっていた。
一部始終を眺めていた柳の木はこんな詩をとなえた。
“手の込んだ悪知恵は身の破滅。だますものもだまされるものも自分のことだけを考えるから”
お釈迦様はこう語り終えられ、この柳の木の精こそ前の世の私であった、と言葉を結ばれた。
タイトルへ戻る
金の羽を与えた白鳥
昔、ブラフマダッタ王がバーラーナシーの都で国を治めていたころの事でる。
ひとりの菩薩があるバラモンの家に生まれた。やがて妻をむかえ三人の娘が産まれ一家は幸せであった。しかし、一番下のスンダリナンダがやっと歩けるようになる頃、彼は妻子を残してあの世へ行ってしまったのである。残された親子は親戚の家政婦として細々と暮らしていくよりなかった。

そのことだけが心配だったのである。彼は金色に輝く羽を広げてこの世を飛び回り、やっと親子四人の居場所を探し当てた。
「なんというやつれようだ。」
金のことで言い争う以外はあまり口もきかない暮らしぶりを見て彼の心は刺すように痛んだ。
「そうだ、私の金の羽は叩き伸ばせばどんな細工にも使える。これで指輪や首飾りをつくればいい値に売れるだろう。」
彼は月明かりの窓にふわりと降り立ち、妻と娘たちを呼んだ。誰もが目を丸くするばかりである。
「信じられないだろうね、私はお前たちの父親なんだよ。お前たちを助けたくてきたのだ」
「あなたが死んだおとうさんなの?」

白鳥は四枚の金の羽を与えて去った。娘たちはそれで指輪やスプーンなどを作り始めた。ただ、母親は羽をそのまま売ってしまった。父の白鳥は月に一度窓辺に降りて金の羽をおいていき、親子の暮らしはどんどん良くなっていった。そんなある日、母親は娘たちに言った。
「ねえ、どうだろう、一枚ずつもらっていたんじゃじれったくてしょうがない。第一男なんていつ気が変わるか知れやしない。この次にきたときにはみんで押さえつけて金の羽を全部むしってしまおう。私たちはいっぺんに大金持ちになれるよ」
「だめよお母さん、おとうさんがかわいそうじゃないの。」
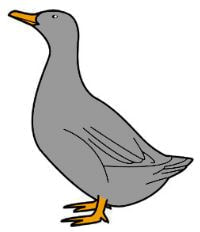
母親は窓に仕掛けをした。白鳥はその罠にかかり、昔の妻によって丸裸にされていった。と、そのとき、むしりとった金の羽はすべて灰色のガチョウの羽に変わった。一文の金になる代物ではなかった。
「チクショー」という金切り声が何度も聞かれ、娘たちは目にいっぱい涙をためていた。
お釈迦様はそう語り終えられ、この金の白鳥こそ前の世の私であったと言葉を結ばれた。
タイトルへ戻る
香り盗人
昔、ブラフマダッタ王がバーラーナシーの都で国を治めていたころの事である。
ひとりの菩薩がバラモンの家に生まれた。彼は成長するとタッカシーラの街へ出て学問を修め、仙人の弟子となって修行者の生活に入った。
ある日、近くの蓮池を巡り、満開の花を眺めて楽しんでいた。水面からはかぐわしい花の香りが漂い、風がさざ波を起こすとその香りは一枚の花びらといっしょに彼の体を包み込むように流れてくるのだった。
「ああ!いい香りだ。つらい修行が吹っ飛ぶようだ。私の体をこの香りで染めてしまいたい。」

彼は驚いてあたりを見回した。誰もいない、人影は池の向う岸で華を蹴散らして蓮根を掘っている爺さんだけだった。
「おーい、おじいさん、何か言ったかい?」
爺さんは振り向いて首を振った。
「風かァ、花びらの落ちる音か、それとも波立つ水のささやきだったか」
修行者はいぶかりながら花の香りを深く吸い込んだ。
「泥棒はおやめ、香り盗人」
声はまた聞こえた。さっきよりもはっきりと、強い調子である。
「誰です、姿を見せてください。香り盗人とは私のことですか?」
修行者は四方に向かって問いかけてみた。声はまた違う方向から聞こえてくる。
「一本の華でも与えられないものをとるのは盗人です」
「そんなことはしない、私はただ、香りをかいだだけです。それを盗人というならあの向こう岸の爺さんはどうです?蓮根泥棒じゃないですか!」
「盗むことに慣れてしまった人に何を言っても聞く耳をもたないでしょう。あなただから言うのです。清らかに生きようとつとめているあなただから、塵ほどの罪も犯してほしくないのです。小さな罪を犯すことに慣れてしまうと、後は大きく生き方まで変わるものです。自分に厳しく、これは修行者の誓いではありませんか?」

「それが甘えというものです。自分で努力して鍛えていってください。」
声のする方向に紫の大きな蝶が舞った。
あっ、この池の精だと修行者はとっさに思った。
お釈迦様はそう語り終えられ、この修行者こそ前の世の私であったと言葉を結ばれた。
タイトルへ戻る
狼の断食
昔、ブラフマダッタ王がバーラーナシーの都で国を治めていたころ事である。

そんな時期ガンジスの岸に近い岩場に、一匹の狼がいた。岩山の裾を水が取り巻き、ひたひたと頂上に向かって増え続けた。餌がない、これで三日狼は何も食べていなかった。
「こりやだめだ、当分腹のたしになるようなものにはありつけそうにないや。まあ、あと十日もして水が引くまで、ひとつ断食の行でもしてみるか」
狼は独り言を言って断食の行を思いついた自分に忌々しさと同時にホッとした気分を味わっていた。
狼の断食がいつまで続いたか、30分もすると彼の頭には丸々肥った野うさぎが思い浮かんだ。
「いけねえ、いけねえ、断食の行だ」
彼は頭を振ってこの妄想を追い払った。そして20分もすると鹿の肉の柔らかい歯ざわりが甦ってくる。
「断食というやつは余計腹の減るもんだ」
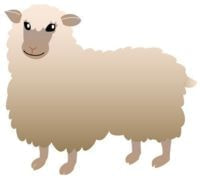
「チキショー、まっいい。なんにしても一度決心した断食の行を破らなかったのが幸いというもんだ。さっやるぞ、十日間の断食」
狼はまた心を取り直した。そのとき虚空に鈴のような声が響いた。
「われは帝釈天である、いま羊の身となって汝の心をためした。その場の成り行きで決心したものはまた成り行きによって破られる。決心とは思い付きではない。暮らしの積み重ねである。汝にどのような暮らしがあったか?」
それは音楽のように余韻を残し、羊の消え去った天空に帝釈天の姿があらわれた。
お釈迦様はそう説き終えられ、このときの帝釈天こそ前の世の私であったと言葉を結ばれた。
タイトルへ戻る
猿をほしがったワニ
昔、ブラフマダッタ王がバーラーナシーの都で国を治めていたころ事である。
ひとりの菩薩が美しい猿の若者としてこの世に生を受けた。

「おまえさん、あの猿、見れば見るほどいい体じゃないか。食べてみたいねえ。殊に心臓の肉は一度食べれば100年長生きするというじゃないの。捕まえておくれよ」
「身の程を知れよ、俺たちは水の中だし、あいつは木の上だよ」
やる気なさそうなオスワニの返事に、ワニの妻はたちまち機嫌を損じて
「フン、できないっていうの!あーあ、こんな甲斐性なしといっしょになるんじゃなかった。」
「ままま、それはだな…。い、いーとも、なんとか打つ手を考えてみよう。」
晴れた日の朝、猿は川面にきらきらする太陽の光を眺めていた。そのとき水がゆっくりと二つに割れて、ワニの夫が姿を現した。
「森の王様、向こう岸は朝日が当たる、果物の熟れるのも早い。どうして向こう岸へ渡ろうとしないんです?」
「あんな遠い向こう岸へボクの力で渡れるわけがないよ。」
「どうです、私の背中に乗って新しい土地を見にいきませんか?さぁさぁさぁ、どうぞ」
猿はその親切を無にしてはと思ってワニの背中に乗った。尻尾をひとなぎ、ワニは水を切ってガンジス川の深みへ泳いでいく。
(ここらでよかろう)ワニは計画通りグイっと体を沈めた。
「おい、ワニさん、これは何の真似だ!まさかボクを」
「そうよ、川のど真ん中じゃどうしようもないだろー。うちの家内がなあ、おまえの心臓とやらをほしがってるのさ」
「ボクの心臓をだって、そ、そ、そいつは、ここに、も持ってきてないよ。」
「なにー? 心臓を忘れた? じゃどこにあるんだ」

「ワニさん、生き物の心臓が木の上にあると思ったのかい、騙そうとするときはいつもあわてているもんだよ」
そういって森の奥へ姿を消した。
お釈迦様はそう説き終わってから弟子たちに向かい“必要なものを求めよ、欲望のものを求めてはならぬ”と謳うように言われ、そのときの猿は前の世の私であったと言葉を結ばれた。
タイトルへ戻る
亀と狐の友情
昔、バーラーナシーの都でブラフマダッタ王が国を治めていたころのことである。
ひとりの菩薩がカモシカに生まれ変わって森の湖の畔に住んでいた。椎の大木には一羽の啄木鳥が巣をつくり、湖には亀がいてこの三匹は仲のいい友達であった。ある日猟師が森にやってきて湖の岸でカモシカの足跡を見つけた。
「そうか、ここへ水を飲みに来るカモシカかがいるんだ、こいつを生け捕りにしたらきっと大もうけができるぞ」

猟師は念入りに罠をしかけ、自分の足跡を消して帰った。朝日が木々の頂に届き、湖に風が渡るとゆっくりと朝もやが融けていく。ねぐらを出たカモシカがいつものように砂浜を駆けていると、後足の砂がじりじりとめり込み始めた。おやっと思った瞬間、バチンというバネの音とともに足首が千切れるほど痛んだ。カモシカは悲鳴を上げた。それを聞いて椎の木から啄木鳥が飛んできた。湖の中から亀が浮き上がってきた。

「おーい、どうしたんだカモシカ君!あー、罠だ。足をやられたんだ。亀君、君の歯で食い込んでいる皮ひもを千切れないかい」啄木鳥(キツツキ)が言った。
「よーし、やってみよう。」
「君たち気持ちはうれしいけど、もうすぐ猟師が来るに違いない。そしたら君たちまで捕まってしまうぞ!ボクのことは構わず逃げてくれ」
「なにを言うんだカモシカ君。こんなときこそ力をあわせなきゃ。ウン、ボクは猟師の家に行って奴が来るのを少しでも遅らせるからね」
言い終わるや啄木鳥は飛び立った。猟師の家の窓を破り、屋根の周りをうるさく飛び回る。猟師は
「いやな鳥だなあ。なにか不吉なことが起こりそうだ。出かけるのは昼からにしよう」
また、寝床にもぐりこんだ。
一方亀は懸命に皮ひもを噛み、歯はもうぼろぼろに欠け、口は血だらけであった。陽はすでに昇り、正午を過ぎた。
「おーい、猟師が来るぞ」
啄木鳥の叫びが聞こえ、矢のような速さで頭上を飛び去っていく。
「亀君有難う、こんなに細くなったんだから力いっぱい引っ張ってみるよ」
皮ひもがプツンと音を立てて切れたとき、猟師が砂浜に姿を現した。カモシカは森へ逃げた。

「せっかくボクを助けてくれたのに、さあ、今度はボクの出番だ。」
カモシカは猟師に目の前にいかにも傷ついて倒れそうな姿で現れた。猟師はやにわに亀を放り出し、投げ縄をもってカモシカを追った。亀は湖に滑り込み、カモシカは森の奥深く姿を消した。
お釈迦様はそう語り終えられこのときのカモシカは前の世の私であったと言葉を結ばれた。
タイトルへ戻る
揉め事を探す山犬
昔、バーラーナシーの都でブラフマダッタ王が国を治めていたころのことである。
ひとりの菩薩が川岸に生えた一本の柳の木に生まれ変わっていた。
ある日、近くに住む山犬の夫婦が
「おまえさん、川の中ほどでびしゃっと言う音がしたでしょう、あれなんだと思う。赤い大きな魚、おいしそうよ。ねえ、捕まえてきてよ」
「そうだな、だけど相手は水の中だぜ」
「ばっかだねえ、誰か水に潜れるやつに捕まえさせればいいじゃないか」

「兄さーん」かわうそは岸に向かって呼んだ。
「手伝ってくれー、ボクだけじゃムリだよー」
兄のかわうそは水を切って助けに行き、三匹の戦いが続いた。やがて腹を見せた魚をかわうその兄弟が岸に運んできた。
「あーあ、疲れた。恐ろしく力の強い奴だった。あ、兄さん、ボクが見つけたんだから先に食べるよ。」
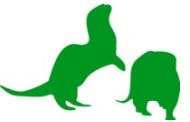
そこへ山犬が現れた。
「おふたりさん、アン、もめてますね。そういうことはまず私に相談したまえよ。いいかい、赤い魚は頭と胴と尻尾でできている、まず、三つに切る。」
そういって山犬は自分の鋭い牙で魚を三等分した。
「さあ、兄さんは頭から、弟の君は尻尾の方から食べ始めるがいい。どっちが先なんてことはないよ。」かわうその兄弟がそれぞれ魚に食いついたのを見て、「こういう風に裁きをつけた私が真ん中の胴をいただくことにしよう。」
こういって一番おいしいところを持っていってしまった。
お釈迦様はそう説き終わってからこのような詩を読まれた。
“まさにかくのごとく、合い争う者は富を失い、争いを種として邪まなる者が富を得る。実に争いは二重の悪である”
そして弟子たちに向かい、そのときの一部始終を見定めた柳の木の精は前の世の私であったと言葉を結ばれた。
タイトルへ戻る
くしゃみの因縁
これはお釈迦さま祇園精舎においでになるときにあるバラモンについて説かれたものである。昔バーラーナシーの都でブラフマダッタ王が国を治めていたころのことである。
王の近くに使えるひとりのバラモンがいた。

賄賂を贈らない刀鍛冶がいた。彼は自分の鍛えた業物の鞘に胡椒の粉を入れて鑑定の日に臨んだ。
王をはじめ大臣の居並ぶ席でバラモンはこの刀を抜いた。一文の金を送ってよこさぬけちな奴と、彼はその刀鍛冶の顔を思い浮かべながらゆっくりと刀身に鼻をあてがった。「はっ、はっ、はっ、はっくしょ〜ん。あ、ああああいてて」くしゃみと同時に鼻先が切り落とされた。血のついた鼻は王の面前にまで転がった。
さて、このブラフマダッタ王には王子がなく、ひとりの王女と甥があった。二人は隣り合った宮殿で育てられ、やがて成長して恋しあうようになった。王はそのことを知って迷い悩んだ末、二人を引き離すことに決めた。
「予の血を引くものはこの二人だけ、二人を夫婦にするのも悪くはないが、それぞれに婿と嫁を持たせれば予の血統がさらに多くなる。血族の増えるのはよいことじゃ」
王はそう考えて甥を宮中から離れた場所に住まわせた。愛し合う若い二人には会いたくても合えない日々が続いた。
「どうしたものか」
ため息混じりに王子はバラモンに問うた。
「なんとかして王子を御殿から連れ出す方法はないものか、そなたは剣相を占うなどというまやかしのほかは何もできぬのか?」
バラモンはしばらく考えた。考えるとき鼻先を動かす癖があった。切り落とされた鼻は蝋で補修され、こしらえ物がついていた。鼻先は昔のようには動かなかった。
「月のない番を選びまする。」バラモンはまず答えた。
「月のない番を選んで姫様を必ず城外にお連れします。明朝、大王様にお目にかかり、このごろ王女様の気分優れぬのは悪運の神に取り付かれておいでのためと申しまする。」
「どこで待てばいいのだ?」
「墓地の後ろ、死体置き場の中がよろしゅうございましょう。厄払いの儀式は死人の中でいたしまする。」
「それもまやかしであろうが…」
「いけませぬか?」
「よい、ただ王女には一群の兵がついてこよう。」
「さればでございます、姫と共にわれらの一隊が近づいたときに胡椒をかいで三度くしゃみをなさいませ、武装の一群といえども生身の兵士でございます、死体の中からくしゃみが起こっては勇気もなえてしまいましょう。私が大声を上げて一番先に逃げ出します。そのとき迷わず姫を抱いて婚礼の誓いを申されませ」
「うん。」
「姫には内々に伝えておきますゆえ」

翌朝、バラモンはブラフマダッタ王の御前に出仕して、ありのままを申し述べた。王はすべてを了解し、大臣を集めると「我が甥を予の跡継ぎとする。」と宣言された。若い二人は相携えて宮殿に帰り、次の王、次の王妃として暮らした。
晴れた朝、東宮へ出仕したバラモンを見て王子は言った。
「太陽に顔を向けるではない。蝋細工の鼻が溶けようぞ。」
バラモンは鼻を押さえてかしこまった。
「くしゃみひとつでそなたは鼻をそぎ落とし、私はくしゃみのために王位につく、くしゃみは善でもなく悪でもないが善としてはたらくときと、悪としてはたらくときがある。これ因縁である。物事は末通って善もなく、末通る悪もない。」
陽は中天に上がりバラモンの鼻が少し融け始めた。
お釈迦様はそう語り終えられ、そのときの王子こそは前の世の私であったと言葉を結ばれた。
タイトルへ戻る
悪逆の王子
これは、お釈迦様が竹林精舎においでになるときダイバダッタについて説かれたものである。
むかしバーラーナシーの都でブラフマダッタ王が国を治めていたころのことである。

ある日大声で命令した。馬の用意が遅いといって側近の者を殴り飛ばしたのはいつものことである。王子ドッタクマーラの一香がガンジス川に着いたとき、空は向こう岸から曇り始めて生暖かい風に水面は波立ってきた。
「この川を泳ぎきるぞ、ついてまいれ」
が、供のものは互いに顔を見合わせるだけで誰一人跡に続くものはなかった。空はいっそう暗くなり風が強まって、雨交じりの暴雨風と変わった。
「おい、みんな。このままお城に帰って、王子様は先にお帰りになったと口裏を合わせようではないか。この嵐だ、ずっと下流に流されていのちも危ういもんだ。」
「そうとも、われらを虫けら扱いにしてきた王子だ魚の餌食になればいい」
供の者たちはこの意見に賛成すると、一目散に城へ駆け戻った。
一方、王子は濁流に押し流されながら助けを求めてわめき叫んだ。だが、周りは風と雨と吼えるような川の流れであった。ふと手に触れた木枝を握った。その枝は中州に根を張る大木の梢であった。王子はその枝にしがみついて真っ暗な一夜を明かした。雨がやんで夜が明けた。
菩薩は小屋を出て、ガンジスの岸に立った。川の真ん中にあった中州はすっかり水の中にかくれ、仰ぐように見た大木も横倒しになって流れに逆らっていた。その木の枝からすすり泣きが聞こえた。
「いかなるものであろうと、死を恐れるものを救わねばならない」
菩薩は神通を現じて中州に飛びいたった。三方にのびた大木の枝、その一つに王子ドッタクマーラが泣いていた。もう一つの枝に年老いた蛇がいた。最後の枝には鸚鵡の雛が震えていた。

「私はバーラーナシーで一・二といわれた金持ちでございました。生前いのちより大事な金をこの中州に埋め、それが気がかりでこうして蛇に生まれ変わりこの金を守っていたのでございます。夕べ死ぬほどの恐ろしさを味わって、初めて金よりも大事なものがあることに気がつきました。この金4億すべて差し上げとうございます。」
鸚鵡が言った。「私はお金はありません、けれども私の一族すべて集まって雪山(ヒマラヤ)の麓から一番良く実った籾を10台の車に積むほど運んでまいりましょう。」
菩薩はそれぞれに頷きながら、静かに微笑した。王子は言った。
「私が王位についたときには尊師よ、かならずわが王城をお尋ねください。お望みのものはなんでも、いやまずもって4種の宴をはってお迎えいたしましょう。」

蛇はすぐに現れ「お待ちしておりました。ここに4億の金がございます。どうぞお持ちください」
「いや、それはそのまま。必要なときに思い出そう」そういい残して鸚鵡の住処に行った。
「鸚鵡よ!」
「お待ちしておりました。私の一族のものがすでに車十台分の籾を集めていつでも運べる手はずでございます。」
「必要なときに思い出すことにしよう」
菩薩はそういってバーラーナシーの都へ向かった。都はドッタクマーラが王位について専横を極めていた。菩薩は城門に立って「王よ!」と呼びかけた。
「城門に立つ乞食を捕らえて殺せ!わしを妬んでのゆすりたかりに相違ない。死刑に処してさらし者にせよ」城内の高楼からドッタクマーラ王の声が響いた。菩薩はそのまま立ち尽くし、
「獣に劣る人あり、獣に劣る人あり」と何度も何度もとなえた。
お釈迦様はそう説き終わって、そのときの王はダイヴァダッタであり、菩薩こそは前の世のわたしであったと言葉を結ばれた。
タイトルへ戻る
鸚鵡の味方
これはお釈迦様が祇園精舎においでになるとき、妻の身持ちの悪さに悩んでる在家のお弟子に向かって説かれたものである。
むかしバーラーナシーの都でブラフマダッタ王が国を治めていたころのことである。
ひとりの菩薩が鸚鵡としてこの世に生まれた。彼には同じ卵から生まれたもう一羽の弟がいた。二羽の鸚鵡は雛のときから心優しい商人に飼われていて、菩薩はポッタパータ、弟はラーダという名で呼ばれていた。
「おはよう!ポッタパータ」
朝、商人が起きてきてそう声をかけると決まってラーダの方が
「オハヨウ!ポッタパータ」とこたえ、
「こんにちは、ラーダ」と話しかけると
「コンニチワ、ラーダ」とポッタパータがこたえた。
商人には子どもがなかったのでこの二羽を本当の子どものように可愛がった。餌はいつも新鮮な果物と上等のひまわりの種であった。羽に虫が入ると気持ちの良い水浴びもさせてくれた。鸚鵡の方もこの商人に父親のように懐いていた。

「旅に出なければならない。商売のためだ。そうだなあ、一月はたっぷりかかるだろう。その間お前たちの世話をしてくれる者がいない。女房はあのとおり気ままな女だ、自分が着飾ることばかり夢中で、鳥の世話など真っ平ゴメン。世話をするどころか焼き鳥にして食ってしまいそうな剣幕でね、寂しいがお別れだな。さっ、出ておいで。そのかわり果物は自分で探すんだよ、空を飛んで風にあたり、雨に打たれて丈夫になっておくれ。この家の回りにひまわりの種は蓄えておいたよ、そして私が帰ってきたらまた姿を見せておくれ。ポッタパータ!ラーダ!」
商人はそういって涙ぐみ、二羽の鸚鵡を空に放った。
商人が旅に出たその日から妻のコシャーヤナの生活は乱れ始めた。まず着るものを買いに出た、気に入ったものを手当たり次第買った。次に履物を買いに行った。着物に合わせて十足の靴を買った。そして次の日は髪飾りを買いに出た。これなら自分に似合うと思ったもの五つと、この方が良くお似合いですと勧められたもの五つとを買った。着物を着替え、靴を履き替え、髪飾りを付け替えて一日を過ごした。三日間それを繰り返して彼女は十分楽しかった。
四日目、新しい着物とそれに一番よく似合う髪飾で街を歩きたくなった。街を歩いて誰もが自分を見ている気がした。羨望の眼差しで自分の美しさに見惚れているように思った。
五日目、また街を歩いた。1人では寂しかった。だれか自分にふさわしい男がいると思った。そして知り合った男と食事を共にした。
六日目、今日も着飾って男と街を歩いた。彼女の視線ひとつでどの男も笑顔で答えた。自分の名を呼ばれたいと思った。「コシャーヤナ」そう耳元で囁かれてみたいと思った。そうして月のうちの十日が過ぎた。
ポッタパータとラーダの二羽の鸚鵡は遠くへ行こうとはしなかった。この家の庭のあちこちに果物の木はあったし、一年かかっても食べきれないほどのひまわりの種が彼らのために用意されていた。主人の心遣いであった。二羽は家の入り口のモッカカの木に止まって主人の帰りを待った。来る日も来る日も帰りを待った。そして二羽が見たものはコシャーヤナの浮気であった。
月の十五日が過ぎるとコシャーヤナはもう外出することをやめた。その代わり毎日男の客があった。来る顔ぶれは毎日変わっていた。
そのたびにコシャーヤナは「待ってたわ、会いたかった」といって男の名を呼び自分の部屋へ招じ入れた。そんな暮らしが月の半分を超えて、やがてこの家の主人が旅に出てから丸ひと月になった。
昼間の暑さが沈んでいってどこかで夕暮れの優しい風が出る頃、街に五十台の馬車が着いてこの家の主人が商売の旅から帰ってきた。先頭の馬車から降り立った主人は、供の者たちにねぎらいの言葉をかけ、我が家の入り口に立った。ポッタパータとラーダはモッカカの木の上で喜びに羽を震わせた。コシャーヤナも着物を裾を翻して玄関を駆け降り、「お帰りなさいあなた、待ってたのよ。会いたかった」といって主人を迎えた。
そのときポッタパータはその声色を真似て
「マッテタノヨ、アイタカッタ サーヴァカ」と男の名を付け加え、ラーダも続けて
「「マッテタノヨ、アイタカッタ シーヴァリ」と二人目の男の名を挙げた。
こうして二羽の鸚鵡は十五人の男の名を次々とコシャーヤナの声色を使って真似ていった。
お釈迦様はそう語り終えられ、そのときのポッタパータこそ前の世の私であったと言葉を結ばれた。
タイトルへ戻る
黒い牡牛の菩薩
これはお釈迦様が祇園精舎にいらしたときのことである。
ある月の明るい夜、比丘たちは車座になってそれぞれの修行生活について話し合っていた。一人の老比丘が言った。
「私が若い頃はじめて仕えた師匠は、いま思うと大ぼら吹きであった。当時は大雄弁家として人気のあるお方であったが、奇跡をおこなう行なうといいながら、ついにただの一度もそれは実行されなかった。」
「それでその師匠を捨てられたか」若い比丘が尋ねた。
「さよう、我からその師を捨てた」
「ならばいま、我らが師、釈迦牟尼世尊は奇跡をおこなわれるか?」
「奇跡をおこなわれようともしない」
「では、なおこの師に仕えられる訳は?」
「自らの業報を担い、運命を使命と転じて自在を得た聖者、釈迦如来はほか比らぶべき者がない」老比丘がそう答えたときお釈迦様は静かにその場所に近づき、次のように語りだされた。
むかしバーラーナシーの都でブラフマダッタ王が国を治めていたころのことである。
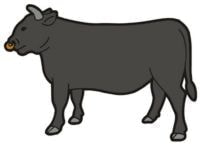
「おまえをこれからホクロという名前にしましょう。さあこっちへおいで。痩せて小さいのは食べ物が十分じゃなかったからです。これからは私の分を減らしておまえに食べさせましょう。そして毎朝藁のブラシでおまえの背中を磨くことにします。歳をとって力はなくなったけれど、毎日磨けばきっと黒曜石の輝きが出てきますよ。もともとそんなに弱い子じゃないんだから」
二年経つとホクロは堂々たる体躯をもつ村一番の雄牛に成長した。両の角に大人を三人づつぶら下げて坂道を登ることができた。子どもなら二十人をその背中に乗せ、急流を泳ぎきることもできた。そして老婦人の藁のブラシはもう雄牛の首までも届かなくなっていた。
「これで私がおまえにしてやれることはなくなりました。おまえはやわらかい草を求めてあの山並みを越えていくこともできるでしょう。水浴びするとき川の深みを恐れることもないのです。さあ、これからは自分ひとりで生きておいでなさい。」老婦人はそう言い聞かせてその日から病の床についてしまった。
雄牛の菩薩は村々をさまよいながら、なんとかして恩返しをしたいと、そのことばかり考えていた。
ある村の船着場に来合わせたとき、500台をも車を連ねた隊商の列に出会った。川の流れは早く、車を引く牛たちは川岸で立ちすくんでいるようであった。鞭を当てる音が続いた。そして牛たちの悲鳴が起こった。

と言いかけた時雄牛の菩薩はゆっくりと列の先頭に進んで、舵棒の中に身を入れた。
「おっ!本気かね」さまざまの声が乱れ飛ぶ中で菩薩は満身の力をこめて最初の百台を引き、急流に身を躍らせた。舵棒が背中に食い込んで血が吹き出た。
「はー、やったぞ!」そういう人間たちの歓声とともに隊商の牛たちも勇気を得ていっせいに川を渡り始めた。500台の車と牛と人間たちは水しぶきをあげて流れを横切った。
その夜、ホクロの母であった老婦人は夢を見た。大きな岩のように育った雄牛がいつの間にかネズミの様に小さくなり、目に涙をいっぱい溜めている夢であった。そして彼女が目覚めたとき、ホクロと名づけた雄牛の菩薩は首に一千金の入った袋を提げて老婦人の門口に帰り着いていた。
「まあ、私のためにしてくれたのかい?背中の皮が破れて骨がみえてるじゃないの!いいんだよ、おまえの稼いだお金でどうして私ひとり楽できるもんですか。さあさあ、また昔のように柔らかい藁でおまえの背中を撫でてあげよう」そういい終わって老婦人はそのまま息絶えたのであった。
お釈迦様はそう語り終えられ、さらに言葉をついで
“比丘らよ、誠実であること、我が身の分限を知って誠実であること、これが人の世の力である。人が奇跡を求め、夢に迷うとき、きっと誠実であることの喜びを失っているものだ”
この雄牛たる菩薩こそ前の世の私であったと言葉を結ばれた。
タイトルへ戻る
五武器太子
これはお釈迦様が祇園精舎におられたとき、努力を捨てた比丘について説かれたものである。
むかしバーラーナシーの都でブラフマダッタ王が国を治めていたころのことである。
一人の菩薩が、この国の王妃の胎内に宿られた。ブラフマダッタ王は800人のバラモンを招き、この子の未来について予言を求めた。

祇園精舎
ブラフマダッタ王はある日太子に行った。
「ガンダーラの国、タッカシーラに武芸に秀でた阿闍梨がいると聞く。汝はその下に行って文武諸芸を学ぶが良い、供は付けぬ。」
太子はタッカシ-ラの師匠の下で五年の修行を積んだ。それは五種の武器をいかに巧みに操るかという技の修行ではなかった。五種類の武器でさんざん打ちのめされる修行であった。師は言われた、
「バーラーナシーの太子よ、今日限りここを去るがよい。私は武器のなんたるかを教えた。ここで学ぶことはそれに尽きる。ただ…」そういって師の阿闍梨は少し言葉を飲み
「ただ、五武器太子と呼ばれるよりは…」と言ったままそのまま瞑想に入られた様子であった。
太子は永年の教えの礼を述べ、五の武器を携えて旅路についた。馬の背で十日、国境の森が見えた。
「若いお方!」村人が太子を呼び止めた。
「あの森を一人で越そうなどと考えてはいけません。」
「なにか訳があるのか?」
「粘毛夜叉が住んでおります。生きてこの森を出たものはありません。」
「食われるのか?」「
「夜叉は獅子の鬣に似た毛で覆われ、矢であれ槍であれその毛で相手の武器を付着させてしまいます。そして武器を奪った後で人間一人丸ごと飲み込んでしまいます。」太子は微笑した。
「よい。私は食われる修行をしてきた。」
そう言い残して森へ入った。森は暗く冷たく粘毛夜叉の妖気に満ちて生き物の気配がなかった。
一里先から大木の梢が揺れ始め、やがて森全体がうなりをはらんと粘毛夜叉が現れた。背の高さはたらの木の頂上に届き、目は茶碗ほどに大きく赤い。二本の牙をむき出した口は鷹のくちばしのように尖っていた。
「止まれ、わが餌食」
夜叉は低く吼えた。太子は弓に矢をつかえ、引き絞って夜叉の胸を狙った。矢は飛んだ。次々に五十本の矢は正確に夜叉の胸板に飛んだ。しかし矢はすべて粘毛夜叉の茶色の毛に吸われるようにくっつくだけで胸を射抜くことはできなかった。太子は槍をとった。太刀をとった。棒をとった。投げ縄を飛ばした。すべての武器をもって立ち向かった。そしてそれらは夜叉の全身を覆う毛に吸い取られるだけであった。太子は拳を振るった。右手が毛に絡みつき左手が吸い取られ、夜叉の胸にぶら下がるように体の自由を失った。
「おれに歯向かうなんざ余程の向こう見ずだな。何奴だおまえは」
「私は五武器太子である、聞いたであろうこの名前を!」
「そんな名は聞かぬが、俺に捕まって震えもしない、命乞いもしない。こういう奴はさぞ歯ざわりが良かろうと楽しみにしているところだ。恐くはないか?」「恐くはない!人間は生まれれば必ず死ぬ、その覚悟はできている。私は武器を頼りにおまえと戦ったのではない。私は、この私の身だけが本当の武器だと思っている。戦いはこれからだ!」
「これから食い殺されようというのにどうして戦うのだ」
「おまえは私を口に入れたが最後、生きてはおれぬ、私の背骨は金剛の剣でできている」粘毛夜叉は少したじろいだ。
「その剣がおまえの内臓を粉々に切り裂くだろう、さあ、私はおまえと刺し違えておまえを退治する」夜叉は太子の凛とした声に心大いに動揺した。
「うー、もし、今日限りこの悪事をやめるなら、おまえ様の弟子にしてもらえるだろうか?」夜叉は太子を抱き下ろしながら少し恥ずかしげに言った。
お釈迦様はこう語り終えて、そのときに五武器太子こそ先の世の私であったと言葉を結ばれた。
タイトルへ戻る
何果樹の木の実
これはお釈迦様が祇園精舎においでになるとき、果物のことなら何でも知っているという優婆塞についてお説きになったものである。
むかしバーラーナシーの都でブラフマダッタ王が国を治めていたころのことである。
ひとりの菩薩が、ある貿易商の息子としてこの世に生まれた。子どもの頃から彼が両親に尋ねることは決まっていた。
「これはなんという花?この木は?あの木の実は食べられるの?」
庭中の植物について知り尽くすと、彼は森へ入って小さな草花にいたるまで詳しく調べるのであった。
「あの子はこれで一人前の商人になってくれるのでしょうか」
「そうよなあー。朝から晩まで草木のことばかり考えているようだ。あれでは先が思いやられる。そろそろ商売のことを教えなければ」両親は将来のことを思うと不安でならなかった。彼が二十歳になったとき、父親は病に倒れた。彼はその日から父に代わって五百台の車、五百頭の馬、五十人の人々からなる隊商を指揮しなければならなかった。
苦しい旅が続いた。国々を巡って商品を売り、新しい産物を仕入れて、また国境を越えるのであった。
草原を抜けて森に入る道ではしばらく馬を休めて、彼は必ず部下に命令した。「いいか、これからは私に断り無しに木の芽、木の実、草や花を何一つ食べてはならぬ。馬が道端の草を食べようとしても私に許可を得てほしい。」隊商はこの命令を固く守った。やがて秋になろうとする頃、一行は大森林を通り抜けてある村に差し掛かっていた。そのとき先頭から馬を反して駆けてくる部下があった。
「だんな様!」彼は弾んだ声で告げた。

「だんな様、この先の村の入り口にマンゴーの大木があります。しかも熟れきった実がそれはもう鈴なりと申していいほどの見事さでございます。馬も疲れております、マンゴーの実で喉を潤して一休みということにしましては」
「うーむ、村の入り口にか」菩薩は馬を走らせて隊商の先頭に立ち、更に鞭を当ててその大木のところまで一息に駆けた。木の周りは一面に緑の草が生えて隊商を休めるにはかっこうの場所であった。
「まて!その実に触れてはならぬ」部下を制しておいて菩薩は仔細にその木を調べた。幹も枝も葉もマンゴーの木と変わりはない、けれども実の色に茶色に熟した実の色に鮮やかな紫が混じっている。
「これはマンゴーではない。何果樹という毒りんごの一種だ。聞いてはいたが見るのは初めてだ」そう独り言のようにつぶやいて隊商に向かって厳しく言い渡した。
「これをマンゴーの実だと誰もが思うだろう、しかしよく考えてみるが良い、村に近いこの丘でマンゴーの実がこれほど熟れるまで何ゆえ村人は採りに来ないのか。この実に触れてはならぬ!触れたものは酔いが全身に回り、これを食したものは死に至る。ナンガジュの実にはハラーハの毒が満ちている、さあ、私たちは青草の茎をかんで渇きを癒そう。癒えたらおのおの武器を抜いてそのまま死んだように大地にひれ伏せ、やがて盗賊の一団が襲ってこよう」
「だんな様、私どもは戦うのですか?」
「いやいや、ただ武器を手にして立つだけでよい、敵は戦う勇気など持たぬ」五十人の一行が車の陰、木の茂み、草原の石に身を横たえて待つとき村がざわめき、家々から飛び出した村人たちがナンガジュの木に集まり始めた。
「ひゃはっはっは、この前のときは牛一頭だった、今度はワシは荷車を手に入れたい」
「ふー、荷車一台でも荷の中身によって値打ちが変わる。絹など積んでいれば笑いが止まらんというもんだ」
「それにしてもこのナンガジュの実は村の宝だ、俺たちゃ働かずに楽ができる。みんなこの人殺しの木の実のおかげさーね。ひゃっははは!」
「いまだ!」菩薩は掛け声と共に剣を抜いて立った。五十人の部下が一斉に立ち上がった
「ひゃーああ」悲鳴をあげて後も振り返らず我がちに逃げ帰る村人たちを見下ろしながら菩薩はまず自らの剣をナンガジュの幹に打ち下ろした。五十人の部下が次々にその剣を振り下ろすうちに実もたわわな枝を震わせて大木は倒れた。木の倒れた後は真っ青な空が広がって世界が広く明るくなったように思われた。
お釈迦様はこう語り終えられて、
「比丘らよ、昔の賢者もまた果物に詳しかったのだ。その隊商の長こそ前の世のわたしであった」と言葉を結ばれた。
タイトルへ戻る
空飛ぶ白象
これはお釈迦様が竹林精舎においでになるとき、ダイバダッタについて説かれたものである。
昔、王舎城においてマカダ王が国を治めていたころのことである。一人の菩薩が一頭の白い象となってこの世に出られた。真っ白な全身にエメラルドに似た緑の目を持ち、それが福徳円満の相を表すものとして国中の評判になっていた。それを伝え聞いたマカダ王はこの象を自分専用の乗り物として召抱え、調教師をつけて一年の間みっちり仕込んだのであった。
象と調教師はまるで兄弟のようであった。
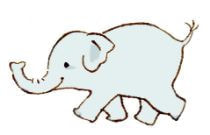
その次の日から、王の巡察が始まった。王舎城の南の部分を三日かけてくまなく巡察し、東の地方北の地方へと移っていった。500人の行列の真ん中を白象は歩いた。仲間のどの象よりも大きく威厳があった。沿道で待ち受ける人々の中から「ホォー」というため息がもれ、雪のような白さ、優雅な歩き振りという囁きはやがて熱気をはらみ、ついに人々は声をそろえて
「転輪聖王の船よ」と爆発にも似た歓声を挙げるのだった。マカダ王は得意であった。
「これほどの象はめったにいるものではない、これを手に入れたのも我が栄光の証しである」といって憚らなかった。
巡察は王舎城の西の部分に入った。王の行列を待つ民衆はここでも口々に白象を讃え、その美しさに感嘆の声を上げた。その頃から王は少しずつ不機嫌になっていった。民衆の歓迎は日増しに高まっているというのに、そのことがどうにも面白くなかった。以前は沿道を埋めた民衆は両手をあげて
「王様!マカダ王万歳!」と歓呼したものだった。
いまはどうだ、王たる私よりも我が乗り物である白象に向かって転輪聖王の船といい、雪山の王者と呼ぶではないか。
「あの象が王たる我をないがしろにしておる」王の心中に嫉妬の焔が燃え上がった。
「あやつを殺す」焔は王にそう決意させた。
「八つ裂きにして殺す。しかしあの大きなものをどうやっ…そうかぁヴェーブッタの頂から突き落としてみては」王はこの陰惨な考えに満足し、すぐに調教師を召しだした。
「何事でございましょうか」
「ほかでもない、ワシのあの白象は十分に調教してあるだろうな?」
「はい、それはもう十二分に仕込んだつもりでございます。」
「ヴェーブッタの山に登れるか?」
「えっ!あの三角の岩山に、でございますか?」
「ただいまから我が目の前で登って見せよ!」否やは言わせぬと王は甲高く叫んだ。
調教師は思い心で白象の背にまたがった。一本の木も生えないヴェーブッタの岩山を、もしうまく登りきったとしてもどうして降りることができるだろうか。おそらく断崖を転げ落ちて刃のような岩でこの身を血に染めることであろう。
「兄弟、どういうわけだ。王はおまえを殺そうとしている、一時はあんなに喜び、この国の宝であるとまで言っておまえを慈しんでいた王が、気でも狂ったのか」白象は調教師を乗せてヴェーブッタを目指した。
王は高楼に昇ってその姿を追った。ヴェーブッタ山麓からその頂上まで道はなかった。誰も登ったことがないからである。白象は進んだ。落ち着いて用心深く進んだ。褐色の岩肌を白象が登るのが城中からも見えた。町中の家の屋根に町中の人が上がった。上がってヴェーブッタの頂上を見た。歩みはだんだん遅くなってはいたが白象の踏みしめる一歩は確実に頂上に向かっていた。
「兄弟、何があったかは知らないがとにかくおまえに無理難題を吹っかけて殺そうとしていることは間違いない。そんな王様なんてこっちからおさらばしようや。さあ、これが頂上だ。兄弟!空を飛ぼう。私もおまえと一緒にいく」調教師が象に向かってそう語りかけたとき、白象は神通力をあらわしてヴェーブッタの頂から虚空を飛んだ。
「象が空をゆく!」高楼で王が叫んだ。家々の屋根で民衆が騒いだ。
「哀王の嫉妬の心が私に虚空を歩ませる」白象の菩薩は一言そういい残した。
お釈迦様はこう語り終えられてそのときの王はダイヴァダッタであり、白象こそ前の世の私であったと言葉を結ばれた。
タイトルへ戻る
砂漠の少年
バーラーナシーの都でブラフマダッタ王が国を治めていたころのことである。
一人の菩薩が貿易商の家に生まれ、二十歳を過ぎるともう一人前の商人として貿易の仕事に精を出していた。彼は五百頭のラクダを使って大キャラヴァンを組み、ラクダの背には商品を満載して都から都へ国境を越えて商売の旅を続けた。
その旅も終わりに近く明日はバーラーナシーの都に帰りつくというとき、一つの難所に出くわした。それは六十里四方の砂漠であった。砂は手のひらですくっても水のように零れ落ち、太陽が昇るとその熱で火のように燃えるのであった。キャラヴァンは太陽が沈むのを待ち、大地が冷えるのを待って夜出発する。航海する船のように星を観測して方向を決め、闇に横たわる砂の海を五百頭のラクダと五百人の人々は一本の黒い帯となって渡るのである。

「断じて諦めてはならん。我らはこの砂漠を越えて必ず都へ帰る。まず足元をよく観察せよ。砂の上に虫の歩いた跡はないか。蛇の這った跡はないか。一粒の草の種が落ちていないか。」
隊長である菩薩は大声で全員に語りかけた。今ここで自分が勇気を失ったらキャラヴァン全体が立ち上がる勇気を失うだろう。
「隊長、これはなんでしょう?このうす緑色のものは」
「あの砂の窪みになにか芽が出ています。」ラクダから降りて二人の隊員の下に歩み寄った隊長は仔細にそれを観察して
「吉祥草の芽だ!水の恵みがなければここに芽を出すはずはない。ここだ、この砂を掘り下げて水を手に入れよう。さあ、最後の力をだせ!」
隊員は交代で鋤をつかい、シャベルを使った。砂の穴は6,7メートルも掘り進んだが水はなく、固い岩盤に出会ってしまった。
「とても無理だぁ、水などありゃしない。力を出すだけ馬鹿馬鹿しいというもんだ。」
「骨折り損のくたびれ儲けというやつさ。隊長、もう止しましょう。それよりもラクダを一頭ずつ殺して、その胃袋の水で喉を潤したほうがずっと楽じゃありませんか」隊員たちは口々にそういって鋤やシャベルを放り出してしまった。「若者はおらぬか!」列の最後尾から一人の少年が駆け寄ってきた。
「いくつになる?」
「17でございます」
「父は」
「おりませぬ」
「母は」
「おりませぬ」
「生来孤独か?」
「仲間がおります。友達がおります。この隊商全部が私の父であり、母であり、兄弟であります。」
少年は広いターバンの下から黒い澄んだ瞳をあげた。水があるなら掘ってもみるがなければ努力するだけ損だという、そういうずるさに染まらない目であった。
「500人の仲間のためにおまえの力がいる。」
「はいっ」

「ここにオアシスが生まれる。そうとも一日でも二日でもゆっくりここに逗留しようじゃないか!」
昇り始めた太陽の下で人々は湧き出る水に潤されながら、天幕を張り、食事の用意を始めていた。しかし少年は砂漠に地下水に飲まれてそのまま帰ってこなかった。
お釈迦さまはこう語り終えられ、一人の比丘にむかって、そのときの少年はそなたの前の世の姿である。精進努力するとは今現になしつつあることをいうのであって、努力したとか、精進してみようとか、過去や未来について言われることではない。今、この瞬間の努力が生死を超える道である。結果のみを思い煩うことは努力する力を弱めてしまうものだと言葉を結ばれた。
タイトルへ戻る
金色の鹿

タイトルへ戻る